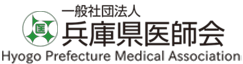年齢とともに物忘れが増え、認知症になるのではと不安になります。WHO(世界保健機構)は、認知症を「いったん発達した知能が、さまざまな原因で持続的に低下した状態。 通常、慢性あるいは進行性の脳の疾患によって生じ、記憶、思考、見当識、概念、理解、計算、学習、言語、判断など多数の高次脳機能の障がいからなる症候群」と定義しています。
物忘れがひどくなると認知症だとわかりますが、初期の頃には、年齢に伴う物忘れなのか、認知症なのかわからないことがあります。また認知症の前段階に軽度認知障害(MCI)といった段階があります。ただしこれら全ての段階には、明確な診断基準がありません。
認知症の予防
英国の医学雑誌Lancetに2024年に掲載された論文では、認知症リスク14項目をすべてクリアすれば最大45%予防(遅らせる・軽減できる)できると発表されました。年齢により3つのライフステージに分け、それぞれに取り組む内容と、どの程度リスクを減らすことができるかを(表1)にまとめています。高血圧、糖尿病、高LDLコレステロール、肥満、運動、喫煙、過度の飲酒など生活習慣に関わる項目が多く含まれています。
(表1)
| 18歳まで | ①教育機会の不足(5%) |
18歳から65歳まで | ②難聴(7%) ③高LDLコレステロール(7%) ④うつ病(3%) ⑤頭部外傷(3%) ⑥運動不足(2%) ⑦糖尿病(2%) ⑧喫煙(2%) ⑨高血圧(2%) ⑩肥満(1%) ⑪過度の飲酒(1%) |
65歳以上 | ⑫社会的孤立(5%) ⑬大気汚染(3%) ⑭視力障害(2%) |
認知症の診断と治療
認知症と同じような症状を引き起こす病気には、うつ病、慢性硬膜下血腫、急性脳梗塞、正常圧水頭症、ヤコブ病、甲状腺機能低下症、ビタミンB12欠乏、極度の貧血、低ナトリウム血症、発熱などがあり、中には治すことができる病気が含まれています。
認知症として有名なものには、アルツハイマー病があります。脳の神経細胞に、アミロイドベータ(Aβ)蛋白が、発症の15~20年前から沈着し始めるという仮説があります。
現在は4大認知症として、アルツハイマー病のように、第一に短期記憶が低下するアルツハイマー型認知症が約70%、(脳)血管性認知症が約20%、幻視や睡眠時の異常行動を起こすレビー小体型認知症が4-5%、前頭側頭型認知症(変性症)が数%との分類があります。
今後 診断技術が進歩すると更に細分化されていくと予想されますが、認知症の類型や重症度により治療法が異なりますので、まずは 医療機関でご相談ください。