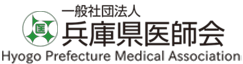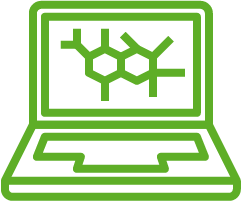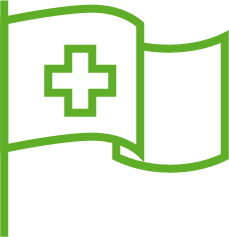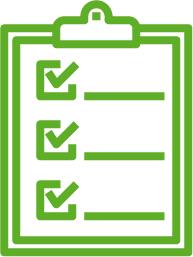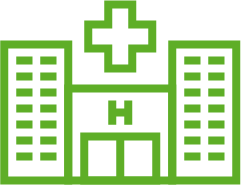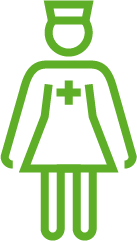[2024/5/25] 兵庫県医師会サイバーセキュリティ研修会の開催について
本研修会は昨日が締切でしたが、継続して募集しますことと、本日以降のお申込みの方には、5/24(金)にまとめてアカウント・資料をご案内致します。 近年、国内外の医療機関を標的とした、ランサムウェア(情報システムを使用不可の状態にした上で身代金を要求するウイルス)を利用したサイバー攻撃による被害が後を絶たないことを踏まえ、サイバー攻撃被害の未然防止を目的として、今年度も標記研修会を下記のとおり開催することになりましたのでご案内申し上げます。 今回は、徳島県つるぎ町立半田病院の事業管理者である須藤 泰史 先生に「サイバー攻撃を受けた経験とその後の取り組み」をテーマにご講演いただく予定ですので、会員の先生方をはじめ、医療機関並びに郡市区医師会の職員の方々も、是非ご参加ください。 なお、準備の都合上、参加希望者には下記の申込方法にて、5月21日(火)までにお申し込み下さるようお願い申し上げます。